- 投稿日:2025年07月08日
- 最終更新日:2025年07月08日
相続手続き、何から始めればいい?|相続&不動産のプロが相続手続きと税金を徹底解説
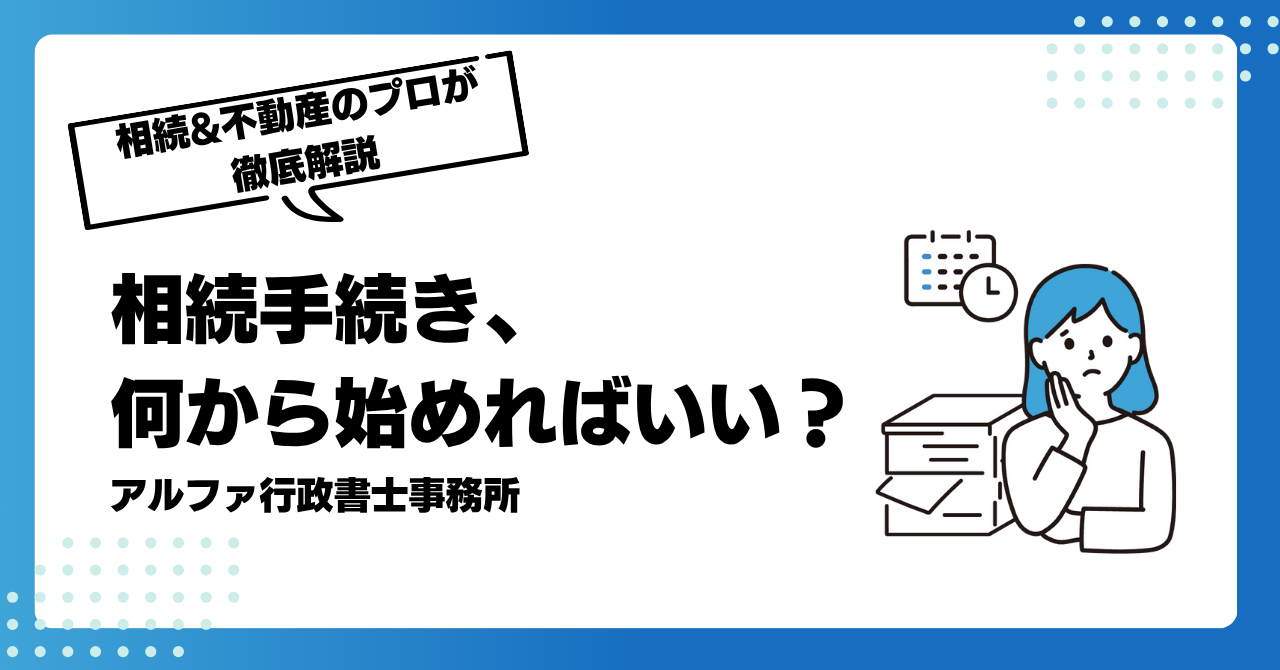
親の介護や相続について考えなくてはならないとき、何を考えればいいか分からない方は多いのではないでしょうか?相続に関して触れる機会は少なく、いざ考え始めたときはそもそも相続とは何をしないといけないのかが分からない方が多くいらっしゃいます。
本記事ではそのような方々に向けて相続の基礎知識から実際の手続きまで分かるようにまとめています。
「何から始めればいいの?」「手続きにどのくらい時間がかかるの?」といった疑問にも、順を追ってお答えしていきますので、ぜひともご覧ください。
目次
相続の基礎知識

被相続人とは
被相続人とは、亡くなられた方のことを指す法律用語です。相続が発生するのは、この被相続人の死亡時点からです。
相続手続きを始める際には、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、最後の住所地の住民票除票等が必要となります。これらの書類は、相続人の確定や相続手続きに欠かせない基本書類となります。
相続人の範囲と順位
法定相続人となるのは、民法で定められた一定の範囲の親族です。相続順位は以下のように定められており、上位の相続人がいる場合、下位の人は相続人とはなりません。
第一順位は配偶者と子どもです。配偶者は常に相続権を持ちますが、子どもについては実子と養子の区別なく同等の権利を持ちます。子どもが既に亡くなっている場合は、その子ども(被相続人から見て孫)が代襲相続します。
第二順位は被相続人の親です。子どもがいない場合に、配偶者と共に相続人となります。親が既に亡くなっており、祖父母が存命の場合は、同じ第二順位として祖父母が相続人となります。
第三順位は兄弟姉妹です。子どもも親もいない場合に、配偶者と共に相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子ども(被相続人から見て甥姪)が代襲相続します。
相続財産とは
相続財産とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産や権利義務の全てを指します。これには、現金、預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。一般的な相続財産には以下のようなものがあります。
プラスの財産としては、不動産(土地、建物)、預貯金、有価証券、生命保険金、死亡退職金、自動車、貴金属、骨董品などが含まれます。また、被相続人が経営していた会社の株式や、特許権などの知的財産権も相続財産となります。
一方、マイナスの財産(債務)としては、住宅ローンの残債、事業用借入金、医療費や介護費用の未払い分などが含まれます。これらの債務も相続の対象となり、原則として相続人が引き継ぐことになります。
相続の手続き
相続手続きの流れと期限
相続手続きは、被相続人の死亡を知った時から始まります。まずは死亡診断書を受け取り、7日以内に死亡届を提出します。その後、以下の流れで手続きを進めていきます。
最初の3ヶ月は重要な判断の期間(熟慮期間)です。この期間内に、相続を受けるか放棄するかの判断を行う必要があります。また、この期間中に相続人の調査や、相続財産の調査も並行して進めます。
相続税の申告が必要な場合は、被相続人の死亡(=「相続の開始」と呼びます)を知った日の翌日から10か月以内に提出すること、そして相続税の納付も同じく10か月以内に行うことが義務付けられています。また、申告が必要かどうかは、相続財産の金額によって判断します。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、申告が必要です。
相続放棄の方法と期間
相続放棄とは、相続人が相続権を放棄する法的手続きです。相続放棄を選択する主な理由は、被相続人の債務が資産を上回る場合や、他の相続人に相続財産の承継を集中させたい場合などです。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。いったん相続放棄をすると取り消すことはできず、その効果は相続人の子どもにも及びます。そのため、安易に判断せず、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。
不動産の相続登記
不動産の相続登記は、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内の日から3年以内に行う必要があります。これは2024年4月から義務化された制度で、正当な理由なく登記を怠ると過料(罰則金)の対象となる可能性があります。
相続登記の手続きは一般的に司法書士に依頼します。必要な書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、不動産の登記事項証明書などです。遺産分割協議が必要な場合は、その協議書も必要となり、複雑かつテクニックが必要ですので、ご注意ください。
相続税の基本

相続税の課税対象と非課税対象
相続税の課税対象となるのは、相続や遺贈によって取得したすべての財産です。ただし、墓地や仏壇などの宗教用財産に関する祭祀財産については非課税となります。
生命保険金や死亡退職金については、一定の金額まで非課税となります。具体的には、生命保険金は「500万円×法定相続人の数」まで、死亡退職金は「500万円×法定相続人の数」までが非課税です。しかし、限度額の範囲を超えた部分については課税対象となり、これを「みなし相続財産」といいます。
相続税の計算方法
相続税の計算は、まず課税対象となる相続財産の総額を算出することから始まります。相続開始前7年以内の贈与された財産も相続財産に加算されることがあります。その総額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額が、相続税の課税対象となります。
実際の税額は、課税対象額を法定相続分で按分し、それぞれに税率(10%~55%の累進税率)を適用して計算します。その後、実際の相続分に応じて各相続人の納付税額を算出します。
相続税の基礎控除と税率
基礎控除額は、令和7年時点で「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。
相続税の税率は、10%から始まり、課税対象額が大きくなるほど段階的に上がっていきます。最高税率は55%で、これは課税対象額が6億円を超える場合に適用されます。配偶者が相続する場合は、一定の要件のもと、配偶者控除により実質的に非課税となる場合がありますので、分割方法は様々な状況を踏まえて検討することをお勧めします。
相続税の申告と納税
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。申告は被相続人の住所地を管轄する税務署に行います。納税については、原則として申告期限までに一括で納付する必要がありますが、納付が困難な場合は、延納制度や物納制度を利用することができます。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、60歳以上の親から20歳以上の子や孫への生前贈与を、将来の相続財産の一部として前倒しで贈与できる制度です。この制度を利用すると、2,500万円までの特別控除が適用され、それを超える部分には一律20%の税率で贈与税が課されます。また、累計2,500万円に達するまで何回贈与しても非課税です。また、相続時精算課税制度の改正により、2,500万円に加えて年間110万円(基礎控除)が創設されました。その年の贈与額が110万円を超えない場合は贈与税の申告も不要をされています。
メリットとデメリット
メリットとしては、特別控除額までの贈与が非課税となること、相続財産を早期に移転できることが挙げられます。また、不動産価格の上昇が見込まれる場合、早期に贈与することで将来の税負担を抑えられる可能性があります。
デメリットとしては、一度この制度を選択すると途中で通常の贈与税制度に戻れないこと、特別控除を超えた部分は一律20%の税率となることが挙げられます。また、将来の相続時に贈与時の価額で相続財産に加算されるため、資産価値が下落した場合は不利になる可能性があります。
適用手続と必要書類
この制度を利用するには、贈与税の申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。必要書類には、戸籍謄本、住民票の写しなどがあります。注意が必要なのは、申告とは別で不動産の贈与を行った場合は別途贈与による移転登記手続き(法務局)が必要となります。
不動産の相続

不動産評価と相続税
不動産の相続税評価額は、路線価方式や倍率方式により計算します。土地は路線価や固定資産税評価額を基に評価し、建物は国税庁の定める一定の方式で評価します。
尚、国税庁が定めている通達等により土地の形状や状況も加味して不動産の評価額を下げることも可能です。
ただし、非常に複雑かつ高度な専門知識を要するため、相続税専門の税理士に相談することをお勧めしています。
不動産の名義変更
不動産の名義変更(相続登記)は、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に行う必要があります。登記には、遺産分割協議書や被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書などの多くの書類が必要です。相続登記を行わないと、将来の売却や担保設定の際に支障が出る可能性があります。
不動産売却に伴う税金
相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税(約20%から40%程)が課税されます。取得費として被相続人が不動産を購入等をした時の金額、諸経費がベースとなります。ただし、建物に関しては減価償却がされますので、建物部分の取得費は注意が必要です。相続開始から3年以内に売却する場合は、取得費加算の特例が適用できる場合があります。
相続トラブルの防止対策
遺言書の作成
家族間のトラブルを防ぐ最も効果的な方法は、遺言書の作成です。公正証書遺言であれば、公証人の面前で作成されているため、信憑性が高く、公証人に原本も保管されることから遺言者の意思を明確に示すことができます。遺言書には財産の分配方法だけでなく相続人への思いや希望を記す(付言事項)ことも大切です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割は、相続人全員の合意による協議が基本です。協議の内容は、遺産分割協議書として書面に残します。協議書には、分割する財産の特定、各相続人の取得分、支払条件などを明確に記載します。
家族間のコミュニケーション
相続トラブルの多くは、家族間のコミュニケーション不足が原因です。日頃から家族で相続について話し合い、各人の希望や考えを共有することが大切です。特に、実家や事業の承継については、早めに方針を決めておくことをお勧めします。
専門家への相談

弁護士と司法書士の役割
弁護士は、主にトラブルが生じた際に相続人の代理人として活動することが一般的です。また、相続人間で話し合っても内容がまとまらない場合やいままで関わったことがない相続人に対する交渉から法的なアドバイスをすることがあります。司法書士は、相続手続きの中で、不動産の名義変更(登記)や相続放棄をする際、家庭裁判所にて手続きが必要な申立てなどを取り扱っています。
税理士の役割
税理士は、相続税の申告や節税対策のアドバイスを行います。特に、経営者が自社の所有している株、不動産や特例の有無の判断など専門的な知識が必要となります。相続税の申告期限に余裕をもって相談することが望ましいでしょう。
相続のプロのアルファ行政書士事務所
上記に書いたように、相続には様々な専門家と連携する必要があります。
一方、どの専門家も相続の中の一部分を担当することが多く、相続を進める全体のパートナーとして伴走することは稀です。
アルファ行政書士事務所は、さまざまな専門家と連携しながら煩雑な相続業務を請け負いつつ、資産を確保できるよう適切に相続を進行します。
また本人の相続サポートだけでなく、今後の将来につながる終活全般のご相談を広く対応しております。
おわりに
相続の手続きは複雑で、時間もかかりますが、一つずつ着実に進めていくことが大切です。このガイドを参考に、まずは自分の状況に合った準備を始めてみましょう。
分からないことや対応が大変と思うことがあれば、専門家に相談することをお勧めします。
アルファ行政書士事務所では、相続の手続きを請け負うことで、みなさまに将来を考える時間、家族と向き合う時間を増やします。お困りのことがあればお問い合わせいただくか、無料相談をご利用ください。
仕事や家事で忙しい毎日かもしれませんが、相続の対応は家族の将来のために重要な投資です。ぜひ、ご自身のペースで準備を進めていってください。