- 投稿日:2025年07月26日
- 最終更新日:2025年07月28日
【遺言書ガイドvol.3】遺言書を作成すべき人の特徴チェックリスト|アルファの相続
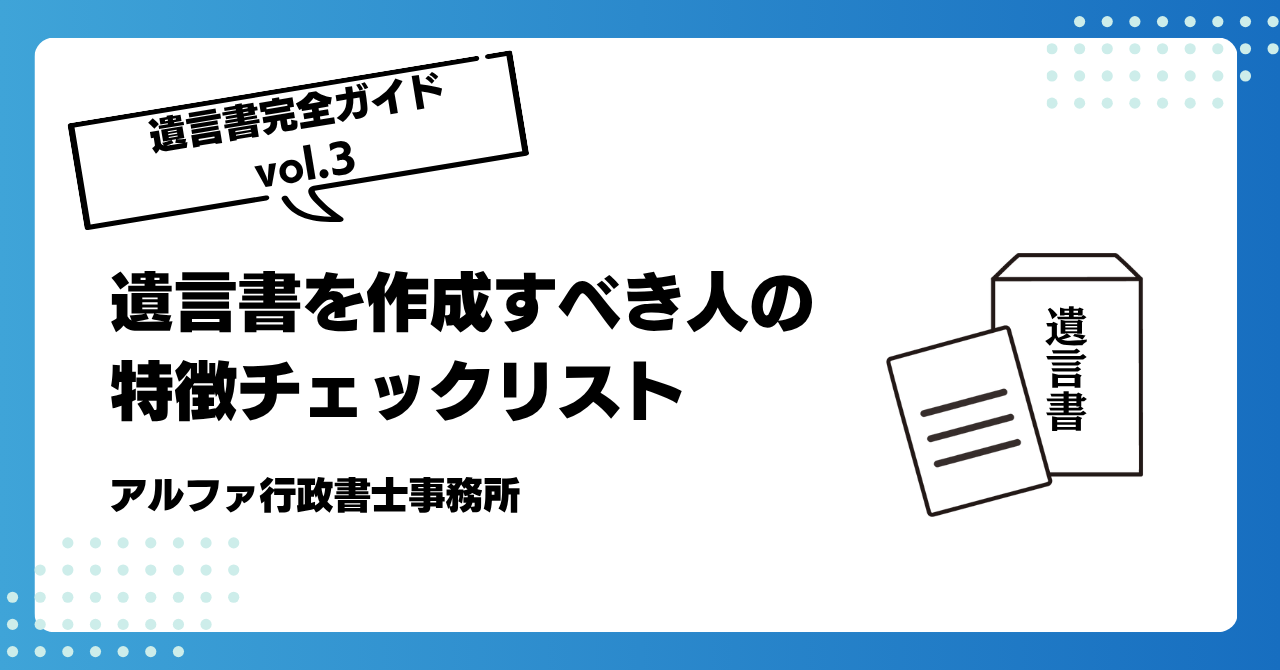
本連載では遺言書を知らない方にも遺言書の全体像について分かるように、連載形式でご説明しています。
第1回は「遺言書とは?遺書との違いと現代における必要性」、第2回は「自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット完全解説」を解説しています。まだお読みになっていない方はぜひともご覧ください。本記事ではどのような人が遺言書を作成すべきかについて解説します。
「遺言書は本当に必要なの?」「まだ早いのでは?」と迷われている方も多いのではないでしょうか。遺言書の必要性は、財産の多寡だけでなく、家族構成や財産の種類、家族関係など様々な要因によって決まります。
相続の専門家として1,500件以上の案件を手掛けてきた経験から、遺言書がないことで深刻なトラブルに発展するケースには共通したパターンがあることが分かります。逆に言えば、これらのパターンに当てはまる方は、早めに遺言書作成を検討すべきということです。
この記事では、遺言書作成を検討すべき人の特徴を具体的なチェックリスト形式でご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせて、遺言書作成の必要性を判断する参考にしてください。
目次
遺言書作成が必須な高リスクケース

以下の項目に2つ以上当てはまる場合は、残された方が大変な困りごとを抱える可能性が高いため、必ず遺言書の作成をお勧めします。
相続人の一人と同居している場合
同居している相続人がいる場合、その方と他の相続人との間で遺産分割について意見の対立が生じやすくなります。同居している方は「親の面倒を見てきたのだから多く相続したい」と考える一方、他の相続人は「法定相続分通りに分けるべき」と主張することが多いためです。
実際のケースでは、長男夫婦と同居していた父親が亡くなった際、自宅の相続を巡って長男と次男が激しく対立し、最終的に家庭裁判所での調停になったケースもありました。事前に遺言書で分割方針を決めておけば、このような争いは避けられます。
再婚をしている場合
再婚されている方の場合、前の配偶者との子どもと現在の配偶者との間で相続権が発生し、複雑な関係になります。お互いに面識がなかったり、感情的な対立があったりする場合、遺産分割協議が難航する可能性が高くなります。
ある60代男性のケースでは、再婚した妻とその連れ子、前妻との子どもの間で相続が発生し、全く面識のない相続人同士で遺産分割を協議する必要が生じました。結果として、弁護士を介しての交渉となり、相続手続きに2年以上を要することになりました。
兄弟・姪甥が相続人になる場合(配偶者・子なし)
お子様がいらっしゃらず配偶者もいない場合、相続人は兄弟姉妹となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子ども(姪や甥)が相続人となります。このような場合、相続人の数が多くなりがちで、全員の合意を得ることが非常に困難になります。
実際のケースでは、独身で子どものいない女性が亡くなった際、相続人が兄弟姉妹とその子ども合わせて8名となり、全員の印鑑をもらうだけで半年以上かかったケースもありました。
子どものいないご夫婦の場合
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、一方が亡くなると配偶者と亡くなった方のご両親又は兄弟姉妹等が相続人となります。高齢の配偶者とご両親又は兄弟姉妹で遺産分割協議を行うことになり、精神的・体力的な負担が大きくなります。
特に配偶者が認知症を患っている場合、成年後見人の選任が必要となり、手続きがさらに複雑化します。遺言書があれば、配偶者が安心して老後を過ごすことができます。
遺言書作成を強く推奨するケース

以下の項目のうち3つ以上に当てはまる方は、将来のトラブル回避のために遺言書作成を強く推奨いたします。
特定の相続人に多く残したい場合
家業を継ぐ子どもに資産を集中させたい、親の介護をしてくれた子どもに多く相続させたい、など特定の相続人への配慮が必要な場合は遺言書が必須です。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、法定相続分を主張する相続人がいれば、希望通りの分割は困難になります。
参考記事:[相続事例]遺言書で実現した、生前お世話になった姉への遺産相続
実子が3人以上いる場合
相続人が3人以上になると、遺産分割協議がまとまりにくくなる傾向があります。2人であれば話し合いで解決できることも、3人以上になると意見が分かれ、調整が困難になることが多いためです。
実際の統計でも、相続人が3人以上の場合の家庭裁判所への調停申立件数は、2人の場合より大幅に増加しています。
自宅しか主な財産がないと思っている場合
「うちは自宅だけだから大丈夫」と考えている方も多いですが、実は不動産こそ最も分割が困難な財産です。現金のように簡単に分けることができず、売却するか共有名義にするか、一人が相続して他の相続人に代償金を支払うかという選択になります。
自宅の評価額が3,000万円で相続人が3人の場合、一人が自宅を相続すると他の2人に1,000万円ずつ支払う必要があります。現金がなければ自宅を売却せざるを得ず、「実家を守りたい」という希望が叶わなくなってしまいます。
財産の分け方がまだ決まっていない場合
「まだ決めていない」「その時になったら家族で話し合う」と考えている方もいらっしゃいますが、実際の相続の場面では感情的な対立が生じやすく、冷静な話し合いは困難になることが多いです。
元気なうちに家族の状況や貢献度を考慮して分割方針を決めておくことが、家族の幸せにつながります。
セルフチェック診断シート

チェック項目一覧
以下の項目について、当てはまるものにチェックを入れてください。
高リスク項目(重要度:★★★)
□ 相続人の一人と同居している □ 再婚をしている
□ 兄弟・姪甥が相続人になる(配偶者・子なし)
□ 子どものいないご夫婦である
中リスク項目(重要度:★★)
□ 特定の相続人に多く残したい
□ 実子が3人以上いる
□ 自宅しか主な財産がない
□ 財産の分け方が決まっていない
□ 相続人に認知症の方がいる
□ 海外に住んでいる相続人がいる
要検討項目(重要度:★)
□ 60歳を超えている
□ 事業を営んでいる
□ 賃貸不動産を所有している
□ 相続税が発生する可能性がある □ 家族関係が複雑である
判定結果
高リスク項目が2つ以上該当 → 遺言書作成が必須です。すぐに専門家にご相談ください。
高リスク項目が1つ + 中リスク項目が2つ以上該当 → 遺言書作成を強く推奨します。早めの検討をお勧めします。
中リスク項目が3つ以上該当 → 遺言書作成を検討してください。将来のトラブル回避のために有効です。
要検討項目のみ該当 → 現時点では緊急性は低いですが、定期的な見直しをお勧めします。
相続で動く金額の大きさを理解しよう

多くの方が「うちはそれほど財産がないから大丈夫」と考えがちですが、実際には500万円、1,000万円といった金額でも十分にトラブルの原因となります。これらの金額は、一般的な家庭にとって決して少ない金額ではありません。
相続は人生で最も大きな財産を手にするタイミングの一つです。取得する金額はさまざまですが、何のルールもない話し合いで分け方を決めることの困難さを理解することが重要です。
実際の調停事例を見ると、争いになった遺産額の多くは1,000万円から5,000万円の範囲内です。「お金があるから揉める」のではなく、「分け方が決まっていないから揉める」というのが実情です。
アルファの相続では、はじめにお客様の状況や家族関係などをお伺いして、円満な相続を実現することを目的としたサポートをおこないます。さまざまなケースがありますが、残された家族が遺産で揉めたり、手間をかけたりしないよう、遺言書で残してあげることが、家族への最大の思いやりと考えています。
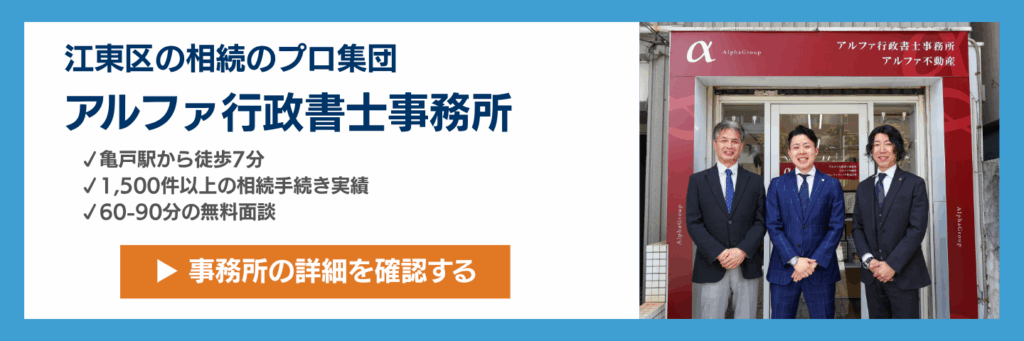
年代別の遺言書作成タイミング
50代:準備期間として最適
50代は遺言書作成の準備期間として最適です。まだ健康で判断力も十分で、家族構成もある程度固まってくる時期です。この時期に一度遺言書を作成し、その後定期的に見直すことをお勧めします。
60代:本格的な検討時期
60代に入ったら、本格的に遺言書作成を検討すべき時期です。定年退職により財産状況も見えてきて、老後の生活設計も具体化してきます。元気なうちに家族のことを考えて作成することが大切です。
70代以上:緊急度が高い
70代以上の方は、遺言書作成の緊急度が高くなります。健康状態の変化により、作成が困難になる可能性もあります。まだ作成されていない方は、一日も早い検討をお勧めします。
安心の遺言書作成はアルファ行政書士事務所にお任せください

チェックリストの結果はいかがでしたでしょうか。該当項目が多かった方は、ぜひ遺言書作成を検討してください。該当項目が少なかった方も、将来的な変化に備えて定期的にチェックすることをお勧めします。
アルファ行政書士事務所では、1,500件以上の相続案件の経験をもとに、お客様一人ひとりの状況に応じた最適な遺言書作成をサポートいたします。チェックリストでリスクが高いと判定された方には、特に重点的なサポートを提供し、将来のトラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。
家族の幸せのために、そして安心できる老後のために、遺言書作成について真剣に考えてみませんか。専門家として、あなたの想いを確実に形にするお手伝いをさせていただきます。
次回は、遺言書作成でよくある失敗事例について詳しく解説いたします。せっかく作成した遺言書が無効になったり、トラブルの原因となったりしないよう、事前に注意すべきポイントをご紹介しますので、ぜひご参考にしてください。
初回相談は無料で承っております。チェックリストで該当項目が多かった方、遺言書作成について詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。あなたの状況に応じた最適なアドバイスをご提供いたします。
次の記事では遺言書作成でよくある残念な失敗事例と対策についてご説明します。
予め失敗事例について知り、要点を抑えて遺言書作成ができるよう、ぜひともご覧ください。