- 投稿日:2025年09月04日
- 最終更新日:2025年09月17日
戸籍収集から財産調査まで|相続手続きの書類準備を効率的に進める方法
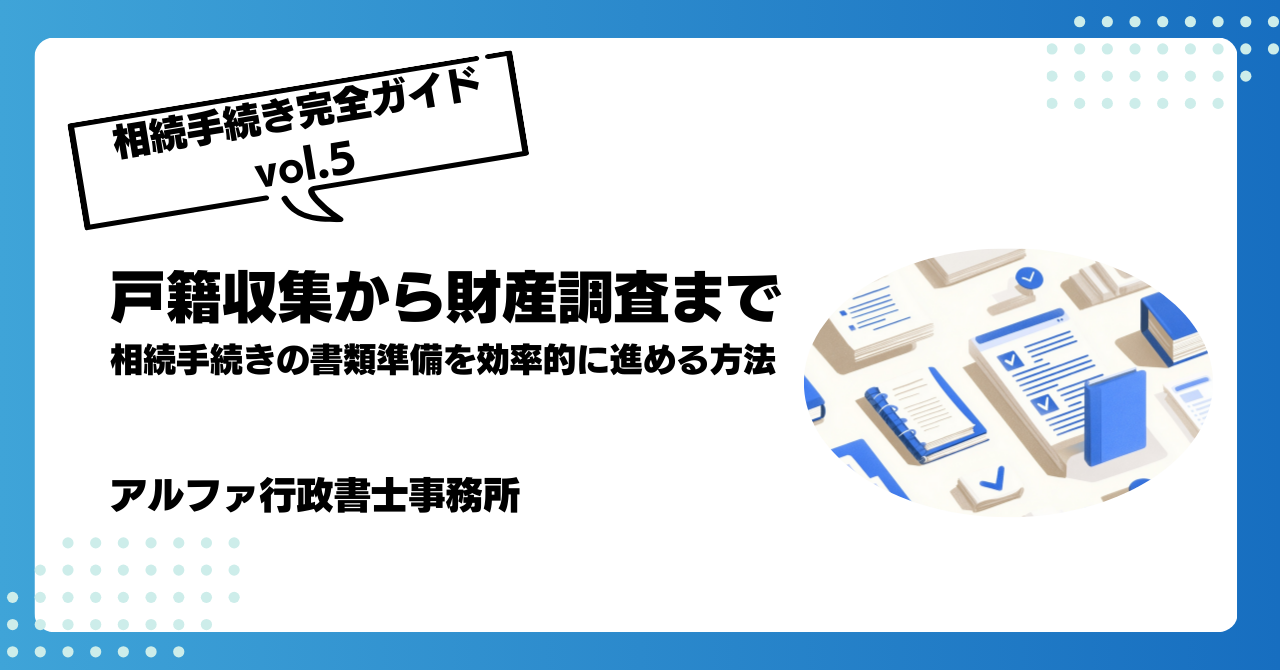
【監修】川井直樹
アルファ行政書士事務所 代表取締役CEO・行政書士
相続手続きで最も時間がかかり、最も重要なのが「書類の準備」です。戸籍謄本の収集、財産の調査、各種証明書の取得など、膨大な書類を正確に集める必要があります。しかし、何をどこから始めればいいのか、どの書類が本当に必要なのか、分からないまま手探りで進める方が多いのが現実です。
アルファの相続では、1,500件を超える相続案件を通じて、効率的な書類準備のノウハウを蓄積してきました。本記事では、実務経験に基づいた具体的な方法とコツをお伝えします。正しい手順と方法を知ることで、書類準備の時間を大幅に短縮し、抜け漏れのない確実な相続手続きを実現できます。
目次
戸籍謄本収集の実際
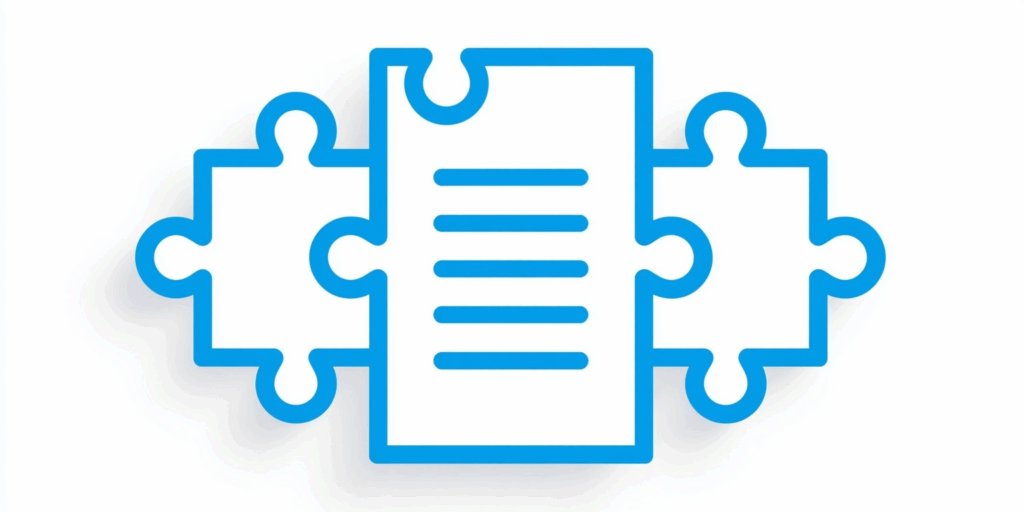
なぜ出生から死亡までの戸籍が必要なのか
相続手続きにおいて、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集めることは、法的に必要不可欠な作業です。
多くの方が疑問に思われるのは、「なぜそんなに遡る必要があるのか」ということです。答えは明確で、相続人を正確に特定するためです。現在の戸籍だけでは、過去の婚姻歴や子供の存在を把握できません。出生から死亡までの全ての戸籍を確認することで、初めて相続人の全体像が明らかになります。
私たちの経験では、「私たちだけだよね」と思っていたケースでも、戸籍調査により予想外の相続人が発見されることがあります。前婚での子供がいたケース、腹違いの兄弟がいたケース、認知した子供がいたケース、養子縁組していた子供がいたケースなど、様々な事例を見てきました。
これらの「隠れた相続人」も法律上は正当な相続権を持っています。きちんと権利自体は発生してしまうため、全員を特定し、遺産分割協議に参加してもらう必要があるのです。
戸籍が複数存在する理由
「戸籍謄本って1個しかないんでしょう?」と思われている方が多いのですが、実際には一人の人生の中で複数の戸籍が作られることが一般的です。
戸籍が新しく作られる主な理由として、法律改正による改製があります。戸籍法の改正により、古い様式から新しい様式に作り替えられることがあります。また、本籍地の変更(転籍)により、引っ越しなどで本籍地を変更すると、新しい本籍地で新たな戸籍が作られます。
結婚による新戸籍の編製も一般的です。結婚すると親の戸籍から抜けて、配偶者と新しい戸籍を作ります。その他、養子縁組、離婚、分籍など、様々な身分行為により新しい戸籍が作られます。
実際のところ、亡くなった時までの戸籍は少なくとも4枚以上あることが一般的です。長生きされた方や、引っ越しが多かった方、離婚・再婚を経験された方などは、さらに多くの戸籍が存在します。私自身も、すでに4〜5枚の戸籍があると思います。
広域交付制度の活用方法とその限界
2024年3月から始まった広域交付制度により、戸籍収集が格段に楽になりました。この制度により、どこの役所でも亡くなった方の戸籍を請求できるようになったのです。
以前は、本籍地のある役所に個別に請求する必要がありました。例えば、生まれが北海道で、その後東京、大阪と転籍していた場合、それぞれの役所に郵送で請求する必要があり、非常に時間がかかっていました。
広域交付制度を利用すれば、最寄りの役所で「亡くなった方の相続人です。出生から死亡までの戸籍をください」と言えば、基本的には全て取得できます。ただし、以下の点に注意が必要です。
まず、直系親族(子、孫、親など)に限られます。兄弟姉妹や甥姪は利用できません。また、時間がかかることもあります。その場で発行されない場合もあり、数日かかることもあります。そして最も重要なのは、抜け漏れの可能性があることです。
抜け漏れチェックの重要性
役所の職員も人間ですので、ミスが発生することがあります。実際、広域交付制度を利用して取得した戸籍に抜けがあるケースをちょこちょこ経験しています。
例えば、平成1年から平成19年までの戸籍と、平成22年から平成30年(死亡時)までの戸籍はあるけれど、平成19年から22年までの3年間の戸籍が抜けているといったケースです。
このような抜けを見逃すと、相続手続きが進められなくなったり、後から追加の手続きが必要になったりします。最悪の場合、相続人を見落とす可能性もあります。
抜け漏れをチェックするポイントは以下の通りです。
戸籍の連続性を確認します。各戸籍の「いつから」「いつまで」の期間が連続しているか確認します。空白期間がないかチェックすることが重要です。
従前戸籍の記載を確認します。新しい戸籍には、どこから転籍・分籍してきたかが記載されています。この記載と実際に取得した戸籍が一致するか確認します。
除籍・改製の理由を確認します。なぜその戸籍が閉じられたのか、理由が明確になっているか確認します。
私たち専門家は、こうしたチェックポイントを熟知しているため、抜け漏れを見逃しません。もし抜けがあった場合は、その本籍地の役所に個別に請求して取得します。
相続関係説明図(家系図)の作成

戸籍から読み取る相続人の確定
戸籍謄本を全て集めたら、次は**相続関係説明図(家系図)**を作成します。これは単なる家系図ではなく、法的に相続人を確定するための重要な書類です。
相続関係説明図を作成する過程で、戸籍の記載事項を一つ一つ確認していきます。出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知など、全ての身分関係の変動を把握し、図式化していきます。
この作業により、法定相続人が誰なのか、各相続人の法定相続分はどれくらいか、代襲相続が発生しているか、相続放棄や欠格事由がないかといったことが明確になります。
隠れた相続人が発見される典型例
実際の相続手続きでは、思わぬ相続人が発見されることが珍しくありません。以下は、私たちが経験した典型的な事例です。
前婚の子供の存在は最も多いケースです。亡くなった方に離婚歴があり、前の配偶者との間に子供がいた場合、その子供も相続人となります。現在の家族が知らないケースも多く、戸籍調査で初めて判明することがあります。
認知した子供の存在も重要です。婚姻関係にない相手との間に生まれた子供を認知している場合、その子供も相続人となります。認知の事実は戸籍に記載されるため、戸籍調査で発見されます。
養子縁組の事実が判明することもあります。普通養子縁組の場合、実親との関係も継続するため、相続関係が複雑になることがあります。特別養子縁組の場合は、実親との関係が切れるため、影響は限定的です。
代襲相続の発生も見落としやすいポイントです。相続人となるべき子が先に亡くなっている場合、その子(孫)が代襲相続人となります。戸籍を丁寧に読み込まないと見落とす可能性があります。
相続人への連絡と協力要請
隠れた相続人が発見された場合、その方々への連絡と協力要請が必要になります。これは非常にデリケートな作業です。
長年連絡を取っていない、あるいは存在すら知らなかった相続人に突然連絡することになるため、慎重な対応が求められます。まず事実関係を丁寧に説明し、相続の権利があることを伝え、今後の手続きへの協力を依頼します。
感情的な問題が絡むことも多いため、中立的な立場の専門家が間に入ることで、スムーズに進むケースが多いです。
不動産調査の重要ポイント

不動産の網羅的な調査方法
相続財産の中で最も価値が大きく、手続きも複雑なのが不動産です。まず、亡くなった方が所有していた不動産を漏れなく把握することから始めます。
多くの方は「親の持っている土地が何平米あるのかもわからない」という状態です。また、本人も忘れていた不動産が発見されることもあります。
不動産を網羅的に調査する方法として、まず固定資産税の納税通知書を確認します。毎年4〜6月頃に送られてくる書類で、課税対象の不動産が全て記載されています。
次に、各市区町村で名寄帳を取得します。その市区町村内で所有している全ての不動産が記載された一覧表です。固定資産税が非課税の不動産も記載されているため、納税通知書より網羅的です。
法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、最新の権利関係を確認します。所有権の詳細、共有持分の有無、担保権の設定状況などが分かります。
登記簿謄本で確認すべき項目
登記簿謄本は、不動産の権利関係を示す最も重要な書類です。以下の項目を必ず確認します。
所有者の氏名と住所が正しいか確認します。相続登記がされていない場合、先代や先々代の名義のままになっていることがあります。
共有持分の有無も重要です。他の相続人や第三者との共有になっている場合、遺産分割や売却時に全員の同意が必要になります。
地目や地積、建物の構造や床面積なども確認します。実際の利用状況と登記上の記載が異なる場合、是正が必要なことがあります。
古い抵当権の発見と対処法
登記簿謄本を見ていると、既に完済しているはずの古い抵当権が残っていることがよくあります。
「返済しても登記簿謄本上の抵当権は自動的に消えない」ということを知らない方が多いのです。銀行から「完済しました」という通知が来ても、別途、司法書士に依頼して抵当権抹消登記をしなければ、登記簿上は残ったままになります。
銀行は完済時に「これ、司法書士さんに消してもらってくださいね」という案内をしているはずですが、多くの方が忘れてしまいます。特に昔の人ほど、この手続きをしていないケースが多いです。
古い抵当権が残っていると、その不動産を売却する際に問題になります。買い手は抵当権が設定されたままの不動産は購入しません。相続登記と同時に抹消することも可能ですが、追加の手続きと費用が必要になります。
古い抵当権を発見した場合の対処法は、まず金融機関に連絡し、完済の確認と抹消書類の再発行を依頼します。金融機関が合併や廃業している場合は、承継先を調べる必要があります。必要書類が揃ったら、司法書士に依頼して抹消登記を行います。
固定資産評価額と相続税評価額の違い
不動産の価値を把握する際、固定資産評価額と相続税評価額は異なることに注意が必要です。
固定資産評価額は、固定資産税の計算基準となる評価額で、市区町村が決定します。納税通知書に記載されている金額がこれに当たります。
一方、相続税評価額は、土地については路線価方式または倍率方式で計算します。建物については固定資産評価額をそのまま使用します。
重要なのは、土地の相続税評価額(路線価)は、一般的に固定資産評価額よりも高くなる傾向があることです。そのため、固定資産評価額だけで相続税の有無を判断すると、後で予想外の相続税が発生する可能性があります。
概算でも相続税評価額を把握したい場合は、国税庁のホームページで路線価を確認するか、税理士や相続専門家に相談することをお勧めします。
金融調査の進め方

預金口座の調査と残高証明書の取得
金融調査では、亡くなった方が保有していた全ての預金口座を特定し、残高を確認します。これは相続財産の把握だけでなく、相続税申告のためにも必要な作業です。
まず、通帳やキャッシュカードから取引金融機関を特定します。自宅を探索し、全ての通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物を確認します。最近はネットバンキングも多いため、パソコンやスマートフォンの履歴も確認が必要です。
次に、各金融機関に対して残高証明書を請求します。これは、亡くなった日現在の預金残高を証明する書類です。
残高証明書の請求には、以下の書類が必要です:死亡の事実が分かる戸籍謄本、請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本、請求者の印鑑証明書、各金融機関所定の請求書。
重要なのは、一つの金融機関につき、その金融機関の情報しか開示されないということです。つまり、A銀行に請求してもB銀行の口座は分かりません。そのため、取引があった可能性のある全ての金融機関に個別に請求する必要があります。
証券口座の調査方法
証券口座の調査は、預金口座よりも見落としやすいため注意が必要です。
まず、自宅で証券会社からの郵便物、取引報告書、配当金の通知などを探します。最近はネット証券も多いため、メールの履歴も確認します。
証券口座が見つかった場合、証券会社に対して残高証明書を請求します。株式、投資信託、債券など、保有している全ての有価証券の明細が記載されます。
証券口座の相続手続きは預金とは異なり、解約ではなく移管が基本となります。相続人が同じ証券会社に口座を開設し、そこに有価証券を移管します。移管後は、相続人の判断で売却するか保有を継続するか決められます。
もし相続人が証券会社に口座を持っていない場合は、新規に口座開設が必要です。これには時間がかかるため、早めの対応が重要です。
相続税申告に必要な取引明細の取得
相続税が発生する場合、より詳細な金融調査が必要になります。特に重要なのが過去の取引明細の取得です。
税務署は、亡くなる前の財産の動きを詳しく調査します。特に注目されるのが、以下のような取引です:多額の出金や送金、定期的な送金(生前贈与の可能性)、亡くなる直前の大きな動き。
そのため、相続税申告では過去5年分程度の取引明細を提出することが一般的です。本来は3年分でも良いという税理士もいますが、安全を見て5年分、場合によっては7年分を取得することもあります。
なぜ7年分かというと、相続税法上、亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻して計算する必要があるからです。この期間内に行われた贈与は、相続税の課税対象となります。
取引明細を取得することで、以下のことが明らかになります:生前贈与の有無と金額、不明な支出の内容、隠れた財産の発見(他の金融機関への送金など)。
通帳がない場合の対処法
最近は通帳レスの口座も増えており、また通帳を紛失しているケースもあります。このような場合でも、適切な手続きにより調査は可能です。
まず、金融機関に口座の有無の照会をかけます。多くの金融機関では、亡くなった方の名前と生年月日で口座の有無を調べてくれます。口座があることが判明したら、残高証明書や取引明細を請求します。
メガバンクや地方銀行、信用金庫、信用組合、JAバンクなど、可能性のある金融機関全てに照会をかける必要があります。手間はかかりますが、財産の見落としを防ぐためには重要な作業です。
効率的な書類準備のコツとタイムライン

並行作業で時間短縮
相続手続きの書類準備は、順番に一つずつ進めるのではなく、並行して進めることで大幅な時間短縮が可能です。
私たちが実践している効率的な進め方は、まず広域交付制度を利用した戸籍収集と、固定資産税納税通知書による不動産の把握を同時に開始します。戸籍が揃い始めたら、相続関係説明図の作成を開始し、並行して金融機関への残高証明書請求を始めます。
不動産が特定できたら、登記簿謄本の取得と名寄帳の請求を同時に行います。これらの作業を並行することで、通常3〜4ヶ月かかる書類準備を、1〜2ヶ月に短縮できます。
専門家に依頼すべきタイミング
全ての書類準備を自分で行うことも可能ですが、以下のような場合は早めに専門家に相談することをお勧めします。
相続人が多数いる場合や、相続関係が複雑な場合(代襲相続、数次相続など)は、戸籍の読み取りが難しくなります。相続税が発生する可能性がある場合は、財産評価の専門知識が必要です。
不動産が多数ある場合や、県外に不動産がある場合も、調査に時間がかかります。時間的余裕がない場合(相続税申告期限が迫っているなど)は、迷わず専門家に依頼すべきです。
よくある失敗と対策
書類準備でよくある失敗として、戸籍の取得漏れがあります。広域交付制度に頼りすぎて、チェックを怠ると発生します。対策として、必ず連続性を確認し、不安な場合は専門家にチェックしてもらいます。
古い戸籍の判読ミスも多いです。昔の戸籍は手書きで、旧字体も多く使われています。重要な部分が読めない場合は、無理せず専門家に確認してもらいます。
財産の見落としも深刻です。特に、ネット銀行やネット証券は見落としやすいです。パソコンやスマートフォンの履歴、メールもしっかり確認します。
期限の管理ミスは致命的になりえます。相続放棄は3ヶ月、相続税申告は10ヶ月という期限があります。カレンダーに明記し、余裕を持ったスケジュールを組みます。
書類準備から見える相続の全体像
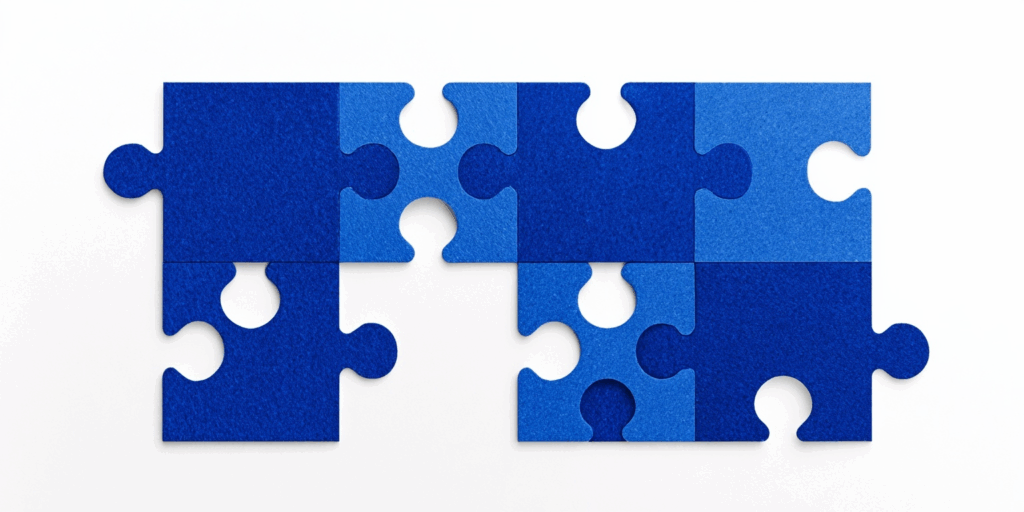
書類が教えてくれること
書類準備を進めていくと、単なる事実関係だけでなく、亡くなった方の人生や家族の歴史が見えてきます。
戸籍からは、人生の軌跡が読み取れます。どこで生まれ、どんな人生を歩んできたのか。結婚、離婚、子供の誕生など、人生の節目が記録されています。
不動産調査からは、財産形成の歴史が分かります。いつ、どのように不動産を取得したのか。ローンを組んで苦労して返済した記録も残っています。
金融調査からは、生活の様子や家族への思いが伝わってきます。子供の学費の振込、孫へのお小遣い、寄付の記録など、お金の使い方から人柄が偲ばれます。
次のステップへの準備
書類が揃ったら、いよいよ遺産分割協議へと進みます。しかし、書類準備の段階で既に、円満な相続への道筋は見えています。
相続人全員が確定し、連絡が取れる状態になっています。財産の全容が明らかになり、分割の選択肢が検討できます。各種手続きに必要な書類が整い、スムーズに進められます。
書類準備は単なる事務作業ではありません。相続という大きなプロジェクトの基礎工事なのです。この基礎がしっかりしていれば、その後の手続きも円滑に進みます。
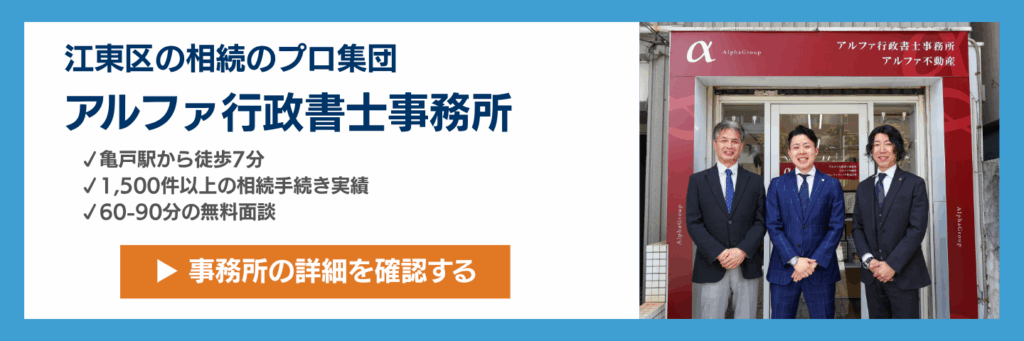
まとめ:確実な書類準備が円満な相続への第一歩

相続手続きの書類準備は、膨大で複雑な作業です。しかし、正しい知識と効率的な方法を知ることで、確実に進めることができます。
本記事の要点をまとめると、戸籍収集では広域交付制度を活用しつつ、必ず抜け漏れチェックを行うことが重要です。出生から死亡まで、連続性を確認しながら収集します。
不動産調査では登記簿謄本で権利関係を確認し、古い抵当権など、問題となる要素を早期に発見します。固定資産評価額と相続税評価額の違いにも注意が必要です。
金融調査では全ての金融機関を網羅的に調査します。相続税申告が必要な場合は、過去5年分の取引明細も取得します。
効率化のポイントは並行作業です。戸籍収集、不動産調査、金融調査を同時に進めることで、大幅な時間短縮が可能です。
これらの書類準備を通じて、相続の全体像が明らかになります。相続人の確定、財産の把握、問題点の発見など、全てはこの書類準備から始まります。
アルファの相続では、1,500件を超える経験を活かし、効率的かつ確実な書類準備をサポートしています。書類の取得代行はもちろん、取得した書類の精査、問題点の発見と対策、次のステップへの準備まで、トータルでサポートいたします。
江東区で安心の相続ならアルファの相続

相続手続きの成否は、書類準備の質で決まると言っても過言ではありません。抜け漏れのない書類準備は、円満な相続への第一歩です。
私たちアルファの相続は、単に書類を集めるだけでなく、その書類から読み取れる情報を分析し、最適な相続戦略を立案します。隠れた相続人の早期発見、問題となる権利関係の把握、相続税対策の必要性の判断など、書類準備の段階から、先を見据えたアドバイスを提供します。
特に、相続税が発生する可能性がある場合や、不動産が複数ある場合、相続人が多数いる場合などは、専門家のサポートが不可欠です。期限に追われて慌てることのないよう、早めのご相談をお勧めします。
書類準備でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。1,500件の経験と専門知識で、確実な書類準備をお手伝いいたします。
初回相談は無料で承っております。相続に関してのご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門家が、あなたの状況に応じた最適なアドバイスをご提供いたします。
監修者

川井直樹
ALPHAGROUP 代表取締役CEO・行政書士
在学中に行政書士資格を取得。国内トップクラスの企業グループでの相続業務経験を経て、ALPHAGROUPを創業。
江東区に事務所を構え、「相続・終活」に特化したサービスを展開。依頼者に寄り添った、安心できる相続手続きをサポートしています。
関連記事
遺産分割協議から手続き完了まで|相続の3つのゴールを確実に達成する方法
[相続手続き完全ガイドvol.1]相続手続きの全体の流れを専門家が解説]
[相続手続き完全ガイドvol.2]相続手続きの最初にやるべき3つのこと|期限管理で失敗しないポイント
[相続手続き完全ガイドvol.3]円満な相続を実現する相続戦略とは?