- 投稿日:2025年08月13日
- 最終更新日:2025年08月13日
【遺言書の専門家が回答】法務局保管制度って何?公正証書との違いを徹底解説|アルファの相続
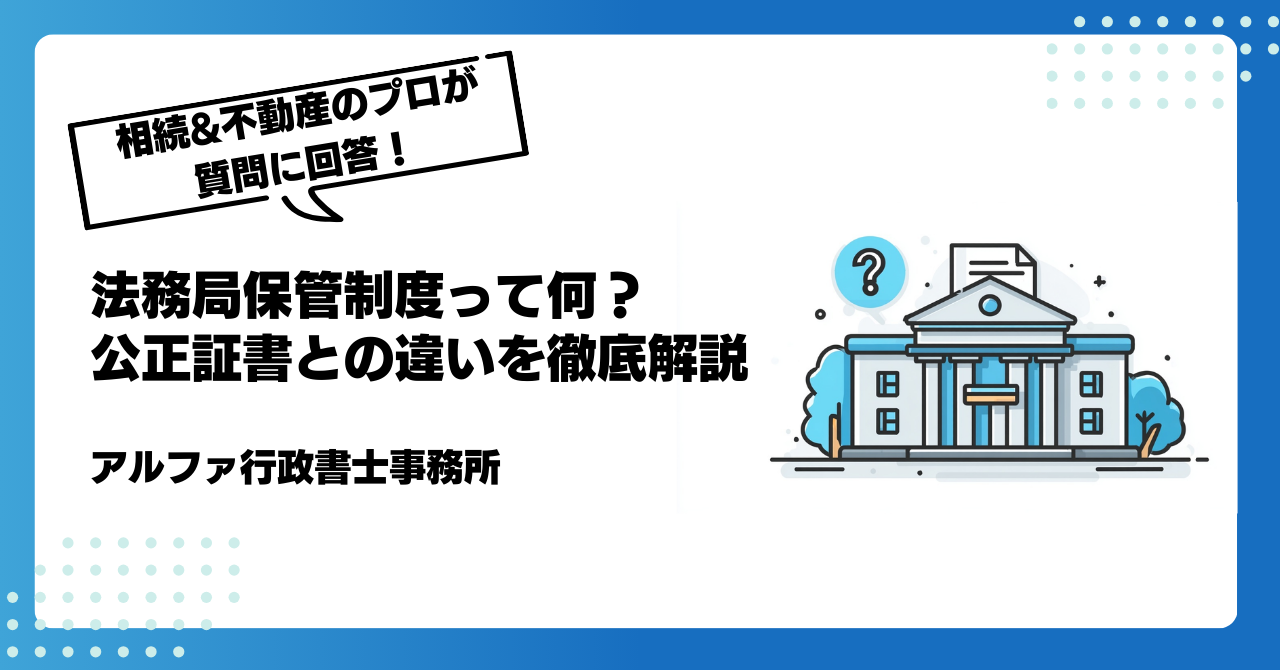
2020年7月から始まった「法務局保管制度」をご存知でしょうか?自筆証書遺言の弱点を補う画期的な制度として注目されていますが、まだまだ知らない方が多いのが現状です。「これなら公正証書でなくても安心では?」というお声もいただきますが、相続の専門家として1,500件以上の案件を手掛けてきた立場から申し上げると、それぞれに明確な違いがあり、すべての方にお勧めできるわけではありません。今回は、法務局保管制度の仕組みと、公正証書遺言との違いについて詳しく解説します。
【Q】法務局で遺言書を保管してもらえる制度ができたと聞きました。これなら公正証書でなくても安心ですよね?
【A】法務局保管制度は確かに画期的な制度ですが、「形式面」の安全性と「内容面」の確実性は別物です。あなたの状況によって最適な選択は変わります。
目次
法務局保管制度とは何か

法務局保管制度は、正式には「自筆証書遺言書保管制度」といい、2020年7月10日から開始された比較的新しい制度です。これは、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を、国の機関である法務局で保管してもらえる制度で、従来の自筆証書遺言が抱えていた様々な問題点を解決することを目的としています。
この制度を利用すると、遺言書の原本は法務局の専用保管庫で厳重に管理され、画像データとしても保存されます。保管申請時には法務局の職員が、日付や署名、押印などの形式的な要件をチェックしてくれるため、形式不備で無効になるリスクが大幅に減少します。
保管手数料は1通につき3,900円と、公正証書遺言と比較して格段に安価です。また、相続開始後は相続人等が「遺言書情報証明書」を請求することで、遺言書の内容を確認でき、従来必要だった家庭裁判所での検認手続きも不要となります。
法務局保管制度の具体的なメリット

法務局保管制度の最大のメリットは、紛失や隠匿、改ざんのリスクが完全に排除されることです。遺言書は法務局という国の機関で保管されるため、災害で失われることも、悪意のある相続人に隠されることもありません。
また、遺言者が亡くなった際、あらかじめ指定された人に遺言書が保管されていることを通知する仕組みもあります。これにより、「遺言書の存在を知らなかった」というトラブルを防ぐことができます。
保管申請時の形式チェックも重要なメリットです。用紙のサイズ(A4)、余白の幅(上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mm以上)、片面記載であることなど、細かな要件がありますが、これらをクリアしていることが確認されるため、少なくとも形式面での不備による無効は避けられます。
法務局保管制度の見落としがちな限界

しかし、この制度には重要な限界があります。最も注意すべき点は、法務局では遺言書の「形式面」のチェックは行いますが、「内容面」についての法的な検証や専門的なアドバイスは一切提供されないということです。
例えば、「自宅を長男に相続させる」と書いた場合、その「自宅」が土地を指すのか建物を指すのか、あるいは両方を指すのかが不明確でも、法務局はそれを指摘してくれません。また、遺留分を侵害する内容になっていても、相続税対策として不適切な内容でも、法務局は関与しません。
さらに、保管申請は必ず遺言者本人が法務局に出向いて行う必要があります。高齢で体調が優れない方や、遠方に住んでいる方には大きな負担となります。代理人による申請は一切認められていないため、どんなに体調が悪くても、本人が出向かなければなりません。
また、相続後の手続きでは、確かに検認は不要ですが、遺言書情報証明書を請求するには、結局のところ相続人全員の戸籍謄本等が必要となります。つまり、検認で必要な書類とほぼ同じ書類を集める必要があり、手続きの負担が抜本的に軽減されたわけではありません。
公正証書遺言との決定的な違い

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が作成に関与する点で、法務局保管制度とは根本的に異なります。公証人は遺言者の意思を法的に適切な文言で表現し、将来のトラブルを防ぐためのアドバイスも提供します。
例えば、遺留分への配慮、予備的遺言(相続人が先に亡くなった場合の規定)、遺言執行者の指定など、素人では気づきにくい重要な点について、公証人が適切に助言し、遺言書に反映させてくれます。
また、公正証書遺言では証人2名の立会いのもとで作成されるため、後から「認知症だった」「強要された」などの主張がされにくく、遺言の有効性が争われるリスクが極めて低くなります。
費用面では確かに差があります。法務局保管制度が3,900円なのに対し、公正証書遺言は財産額に応じて数万円から十数万円程度かかります。しかし、この差額を「専門家のチェックと助言」「より高い法的安定性」への対価と考えれば、決して高額とは言えません。
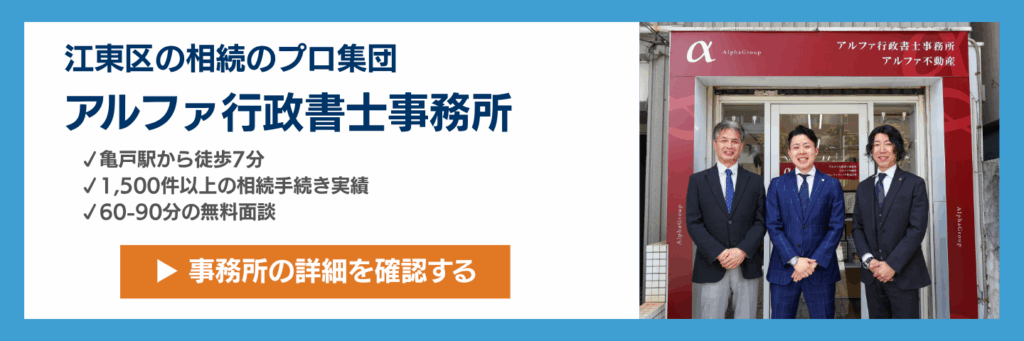
どちらを選ぶべきか – 状況別の選択指針

財産構成がシンプルで、相続人も少なく、特に複雑な事情がない場合は、法務局保管制度でも十分な場合があります。例えば、預貯金と自宅だけで、相続人は配偶者と子供だけ、という典型的なケースです。
一方、以下のような場合は公正証書遺言を強く推奨します。再婚されている方、お子様がいらっしゃらないご夫婦、事業を営まれている方、不動産が複数ある方、相続人の中に行方不明者や認知症の方がいる場合などです。これらのケースでは、専門家の助言なしに適切な遺言書を作成することは困難です。
また、遺言書の内容に少しでも不安がある場合、相続税対策も含めて検討したい場合は、最初から公正証書遺言を選択することをお勧めします。
江東区で安心の遺言書作成はアルファの相続に

法務局保管制度は、従来の自筆証書遺言の弱点を補う優れた制度です。しかし、「形式面の安全性」と「内容面の適切性」は別物であることを理解しておく必要があります。
遺言書の目的は、単に作成することではなく、あなたの意思を確実に実現し、残された家族がスムーズに相続手続きを進められるようにすることです。この観点から、それぞれの制度の特徴を理解し、ご自身の状況に最適な方法を選択することが重要です。
アルファ行政書士事務所では、法務局保管制度の利用サポートから公正証書遺言の作成まで、幅広く対応しております。どちらの方式が適しているか迷われている方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料で承っております。