- 投稿日:2025年07月27日
- 最終更新日:2025年07月27日
【遺言書完全ガイドvol.4】遺言書作成でよくある残念な失敗事例と対策|アルファの相続
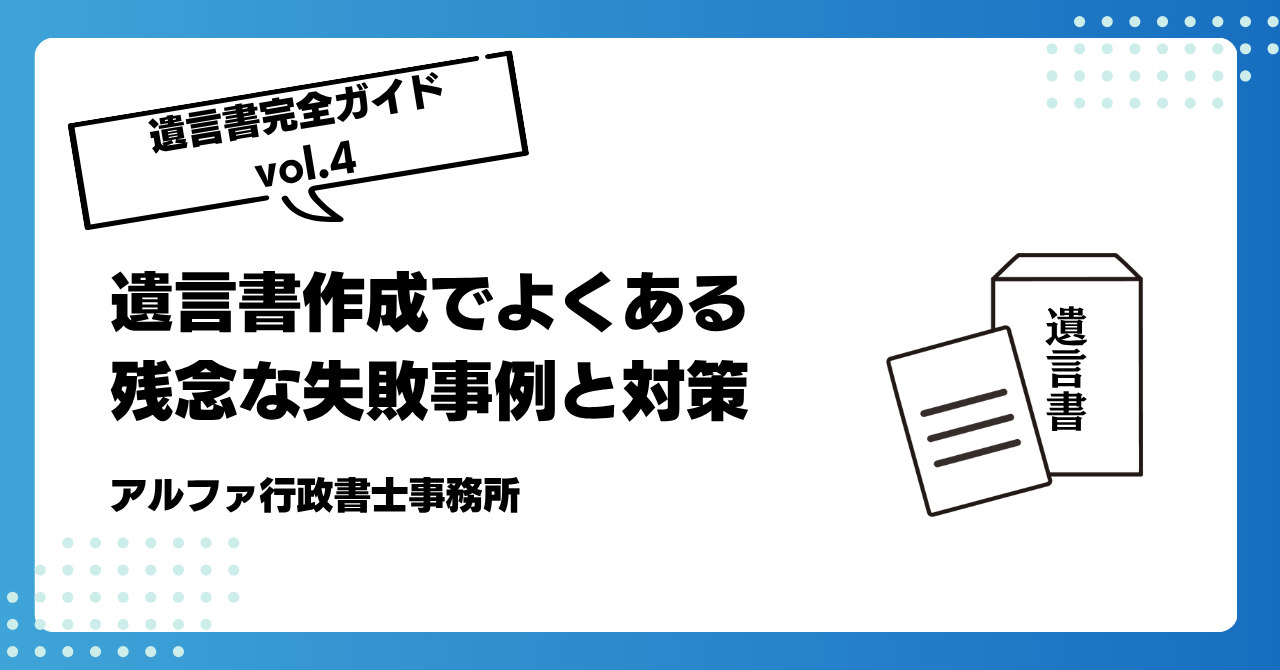
本連載では遺言書を知らない方にも遺言書の全体像について分かるように、連載形式でご説明しています。過去の記事は下記よりご覧ください。
第1回:遺言書とは?遺書との違いと現代における必要性
第2回:自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット完全解説
第3回:遺言書を作成すべき人の特徴チェックリスト
本記事では、遺言書制作でのよくある失敗事例をご紹介します。
遺言書を作成すること自体は素晴らしい判断ですが、残念ながら「作成したものの、いざという時に使えなかった」という事例が後を絶ちません。相続の専門家として1,500件以上の案件を手掛けてきた中で、せっかく作成した遺言書が無効になってしまったり、内容の不備により相続人間でトラブルが発生したりするケースを数多く見てきました。
遺言書の作成は「書けば終わり」ではありません。法的要件を満たし、将来の相続手続きがスムーズに進むよう配慮された内容でなければ、本来の目的を果たすことができません。また、家族関係や相続税への配慮を欠いた遺言書は、かえって家族間の争いの火種となってしまう可能性もあります。
この記事では、実際に遭遇した失敗事例を基に、遺言書作成時によくある落とし穴と、それらを回避するための具体的な対策について詳しく解説いたします。これから遺言書作成を検討される方の参考として、ぜひお役立てください。
目次
ケース1:自筆遺言書が無効になってしまった事例
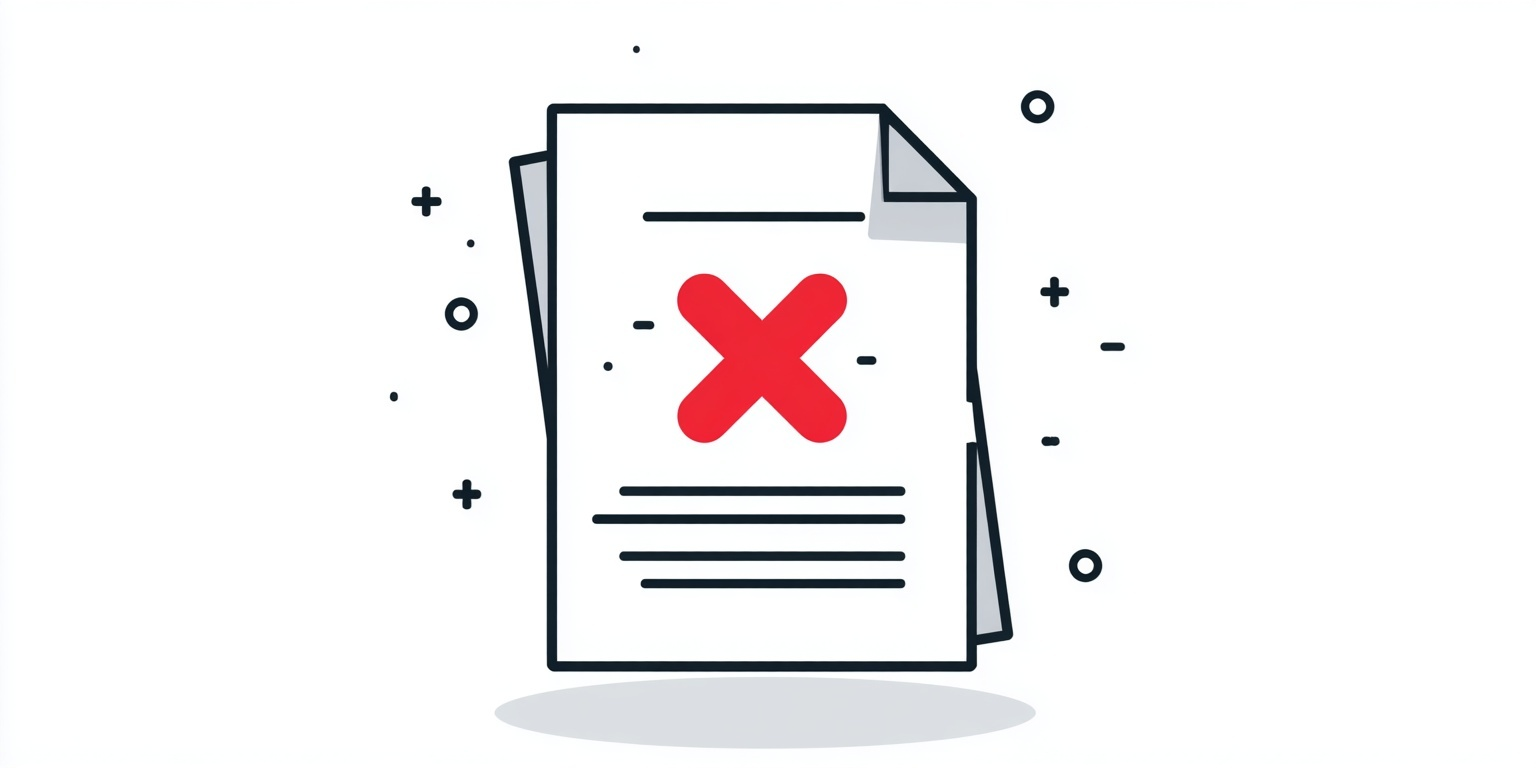
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、法的要件を満たさずに無効となってしまうケースが非常に多いのが実情です。実際に相談を受けた事例の中でも、最も多いのがこの「形式不備による無効」です。
ある70代男性のケースでは、ご自身で遺言書を作成し、自宅の金庫に大切に保管されていました。しかし、相続が発生して家族が発見した遺言書には、作成日付として「令和〇年○月吉日」と記載されていました。民法では遺言書の作成日付を「特定できる形で記載する」ことが要件とされており、「吉日」という曖昧な表現では作成日を特定することができません。このため、せっかく作成された遺言書は法的に無効となってしまいました。
別のケースでは、80代の女性が健康なうちに遺言書を作成されましたが、途中で内容を訂正した際の訂正方法に問題がありました。遺言書の訂正には厳格な手続きが定められており、訂正箇所に押印し、訂正した旨を付記して署名する必要があります。しかし、この女性は単純に線で消して上書きしただけで、正しい訂正手続きを行っていませんでした。結果として、訂正部分が無効となり、遺言者の真意とは異なる内容で相続手続きが進むことになってしまいました。
さらに深刻な事例として、認知症が軽度に進行した状態で作成された遺言書が、後に意思能力不足を理由として無効とされたケースもあります。遺言書は作成時に十分な判断能力(意思能力)があることが前提となりますが、認知症の進行により判断能力に疑問が生じた場合、遺言書の有効性自体が争われる可能性があります。
これらの失敗を防ぐためには、まず民法で定められた遺言書の法的要件を正確に理解することが不可欠です。自筆証書遺言の場合、全文を自筆で書くこと、正確な日付を記載すること、署名・押印をすることが基本要件です。また、訂正する場合は正しい手続きに従い、不安がある場合は新しく書き直すことをお勧めします。
最も確実な対策は、作成前に専門家のアドバイスを受けることです。たとえ自筆証書遺言を選択する場合でも、事前に専門家に相談することで、形式面での不備を防ぐことができます。また、作成後も定期的に内容を見直し、法改正や家族状況の変化に対応することが重要です。
ケース2:公証役場で素人だけで作成した結果の不備
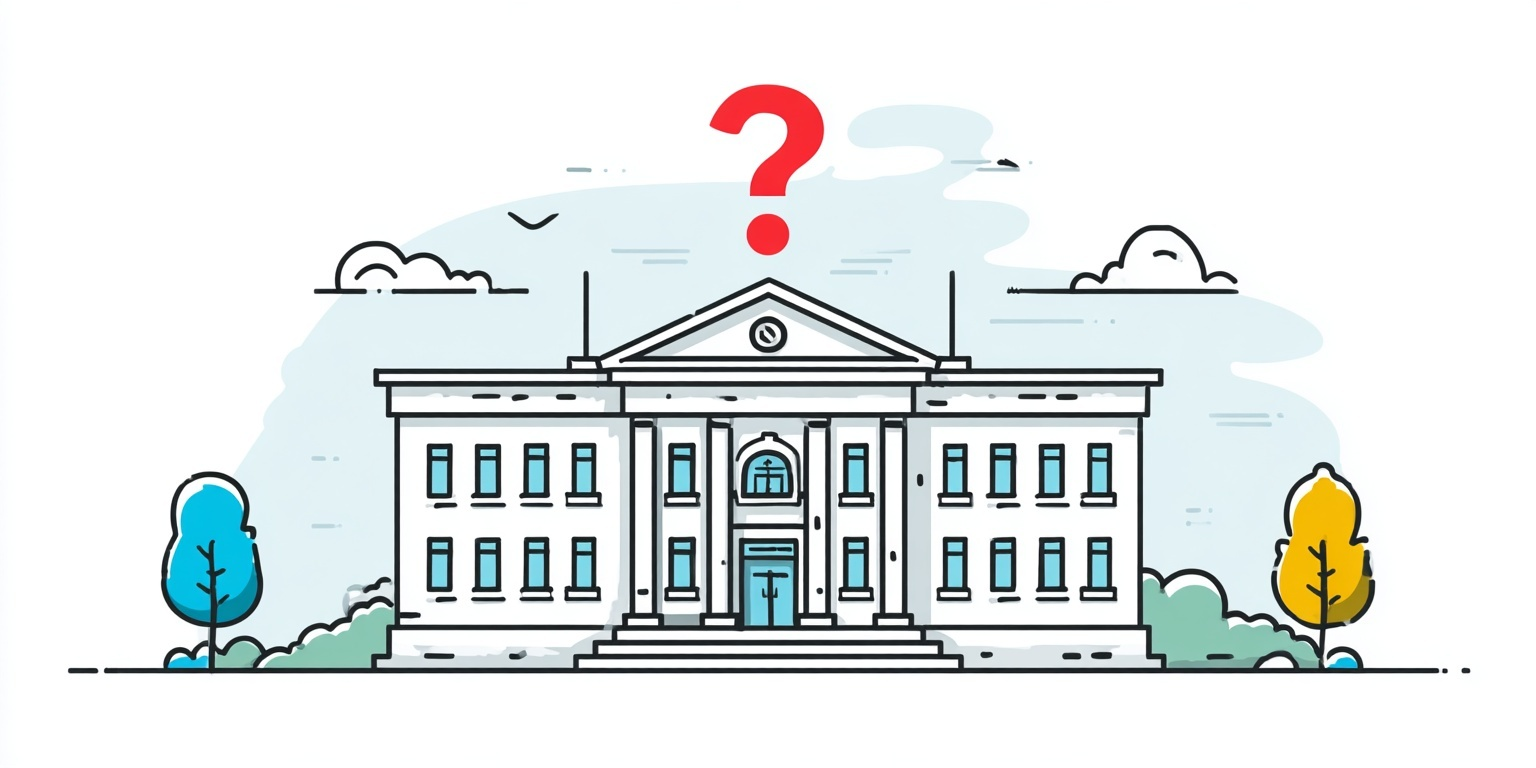
公正証書遺言は最も安全な遺言書作成方式ですが、「公証役場で作成すれば完璧」と考えるのは大きな間違いです。公証人は法的な不備がないかどうかは確認してくれますが、相続税対策や将来の手続きのしやすさ、家族関係への配慮といった実務的な観点からのアドバイスは提供してくれません。
実際にあった事例として、都内在住の60代のご夫婦が、専門家に相談せずに直接公証役場に出向いて遺言書を作成されたケースがあります。ご夫婦には2人の息子がおり、長男夫婦と同居していました。遺言書では「自宅と預貯金の大部分を長男に、次男には預貯金の一部を相続させる」という内容で作成されました。
しかし、この遺言書には重大な問題がありました。まず、相続税の計算を一切考慮していなかったため、長男が相続する財産には多額の相続税が発生することが判明しました。自宅の評価額が高く、預貯金と合わせると相続税の基礎控除額を大きく上回っていたのです。長男は相続税を支払うために自宅を売却せざるを得ない状況に追い込まれてしまいました。
さらに、不動産の記載方法にも問題がありました。「自宅を相続させる」という曖昧な表現で記載されていたため、正確な物件の特定ができず、法務局での名義変更手続きで追加の書類が必要となり、手続きが大幅に遅れることになりました。
また、遺言執行者の指定が漏れていたことも大きな問題でした。遺言執行者が指定されていない場合、相続人全員で遺言の内容を実行する必要があり、手続きがかなり複雑化します。
別の事例では、夫婦でそれぞれ遺言書を作成したものの、互いの遺言書の内容に相違が生じていたケースもありました。夫の遺言書では「妻が先に亡くなった場合、全財産を長男に相続させる」となっていたのに対し、妻の遺言書では「夫が先に亡くなった場合、自分の固有財産は長女に相続させる」となっていました。このような内容であると、実際に相続が発生した際に混乱が生じ、相続人間でトラブルになる可能性があります。
これらの失敗を防ぐためには、公正証書遺言を作成する場合でも、事前に相続の専門家に相談することが重要です。専門家は相続税の概算、不動産の正確な記載方法、遺言執行者の選定、家族関係への配慮など、公証人がカバーしない実務的な観点からアドバイスを提供します。
また、遺言書作成後も定期的な見直しが必要です。相続税法の改正、不動産価格の変動、家族構成の変化などにより、作成時には問題なかった内容が、時間の経過とともに不適切になる場合があります。3年から5年に一度は専門家に相談し、内容の見直しを行うことをお勧めします。
ケース3:遺留分を考慮しなかったトラブル事例
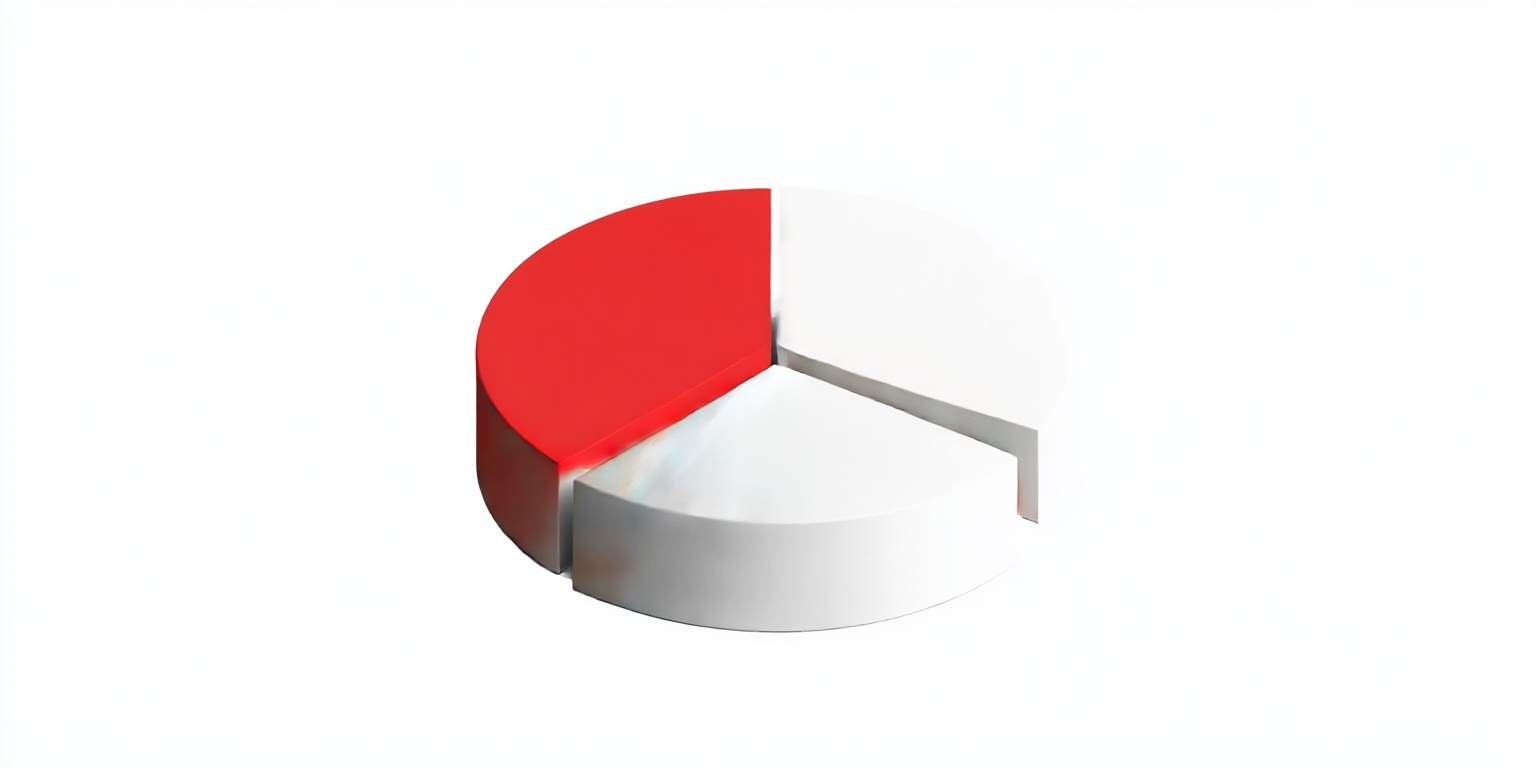
遺留分は相続における重要な概念の一つですが、遺言書作成時に十分な配慮をしなかったことにより、深刻な家族間トラブルに発展するケースが多発しています。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることができる相続分のことで、遺言書の内容に関わらず法的に保障された権利です。
参考:遺留分とは?
実際にあった事例として、80代の父親が「長男に全財産を相続させる」という内容の遺言書を作成したケースがあります。父親としては、長男が家業を継ぎ、母親の介護も担当していることから、すべての財産を長男に相続させることが適切だと判断していました。しかし、この判断には次男の遺留分への配慮が全く含まれていませんでした。
相続が発生した後、次男は自分の遺留分を主張し、長男に対して遺留分侵害額請求を行いました。法定相続分の2分の1が遺留分となるため、次男の遺留分は全体の8分の1に相当しました。相続財産が4,000万円だったため、次男は500万円の支払いを長男に求めることになりました。
長男は遺言書通りに相続したものの、その大部分が不動産であったため、現金で500万円を用意することができませんでした。結果として、父親が残した自宅を売却せざるを得なくなり、父親の「長男に家を継がせたい」という本来の意思に反する結果となってしまいました。さらに深刻なのは、この出来事をきっかけに兄弟関係が完全に破綻してしまったことです。
別の事例では、再婚家庭における遺留分トラブルがありました。60代で再婚した男性が、後妻とその連れ子に全財産を相続させる遺言書を作成しました。しかし、前妻との間の子どもたちの遺留分を全く考慮していなかったため、相続発生後に激しい争いが生じました。前妻の子どもたちは遺留分侵害額請求を行い、法廷での争いに発展してしまいました。
遺留分の計算は複雑で、相続人以外に関しては相続開始前1年間の贈与や、相続人に対する特別受益なども考慮する必要があります。また、遺留分侵害額請求権は相続開始日から10年間、相続があったことを知った日から1年以内に行使可能であり、この期間中は相続財産の処分にも制約が生じる場合があります。
遺留分トラブルを防ぐためには、まず遺留分の仕組みを正しく理解することが重要です。配偶者と子どもがいる場合、配偶者の遺留分は4分の1、子どもの遺留分も4分の1(複数の子どもがいる場合は人数で等分)となります。両親のみが相続人の場合は6分の1、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を侵害する可能性がある遺言書を作成する場合は、事前に遺留分権利者と話し合いを行い、理解を得ておくことが重要です。また、遺留分相当額を現金で用意しておく、生命保険を活用して現金を確保しておくなどの対策も有効です。
相続は機械的にに手続きを進めるのではなく遺族の感情も大きく影響するため、アルファの相続では感情に寄り添ったサポートが重要と考えています。
さらに、遺言書に「付言事項」として、なぜそのような分割をするのかという理由や家族への想いを記載しておくことも大切です。法的効力はありませんが、遺族の理解を得やすくなり、感情的な対立を避ける効果が期待できます。
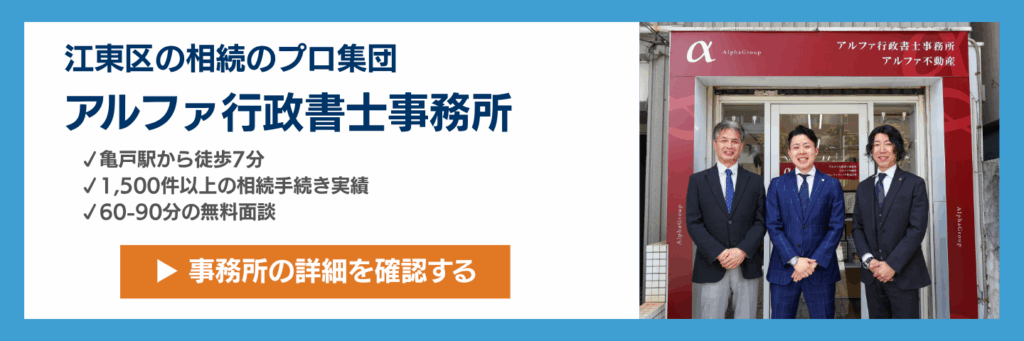
失敗を防ぐための5つのチェックポイント

これまでの失敗事例を踏まえ、遺言書作成時に必ず確認すべき5つのポイントをご紹介します。
第一に、専門家への相談は必須です。自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても、作成前に相続の専門家に相談することで、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。法的要件の確認だけでなく、相続税対策、遺留分への配慮、将来の手続きのしやすさなど、総合的な観点からのアドバイスを受けることが重要です。
第二に、定期的な見直しを行うことです。遺言書は一度作成すれば終わりではありません。相続税法の改正、家族構成の変化、財産状況の変動などにより、作成時には適切だった内容が時代に合わなくなる場合があります。3年から5年に一度は内容を見直し、必要に応じて更新することをお勧めします。
第三に、家族への説明と理解の促進です。遺言書の内容を家族に秘密にしておくことが必ずしも良いとは限りません。可能な範囲で家族に遺言書の存在や大まかな内容を伝え、理解を得ておくことで、相続発生時のトラブルを防ぐことができます。
第四に、遺言執行者の適切な選定です。遺言執行者は遺言の内容を実現するための重要な役割を担います。相続人の中から選ぶ場合は利害関係に注意が必要で、公平中立な第三者である専門家に依頼することも検討すべきです。
第五に、税務面での配慮を忘れないことです。相続税の基礎控除額や税率、各種特例の適用要件などを考慮し、税負担を軽減できる分割方法を検討することが重要です。特に不動産が多い場合は、相続税の支払いのために不動産の売却が必要になる可能性も考慮する必要があります。
安心の遺言書作成はアルファ行政書士事務所にお任せください

遺言書作成における失敗は、単なる手続き上の問題にとどまらず、大切な家族の関係を破綻させてしまう可能性もあります。せっかく家族への想いを込めて作成する遺言書が、かえって争いの原因となってしまっては本末転倒です。
アルファ行政書士事務所では、1,500件以上の相続案件を通じて蓄積した豊富な経験をもとに、失敗のない遺言書作成をサポートいたします。法的要件の確認はもちろん、相続税対策、遺留分への配慮、家族関係への配慮など、総合的な観点からアドバイスを提供し、真に家族の幸せにつながる遺言書の作成をお手伝いします。
次回は、遺言書作成の具体的な流れについて、公正証書遺言を中心に詳しく解説いたします。約1ヶ月半の作成期間に何を行うのか、どのような準備が必要なのかを具体的にご紹介しますので、ぜひご参考にしてください。
初回相談は無料で承っております。遺言書作成でお悩みの方、既に作成済みの遺言書の見直しをお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。専門家の目で現状を診断し、最適な解決策をご提案いたします。